140807_朝顔 ― 2014/08/12 01:16
140808_朝顔 ― 2014/08/12 01:18
140808_あら苧 ― 2014/08/12 01:19
140808_木をいじめること ― 2014/08/12 01:21
140809_常套句だったらしい ― 2014/08/12 01:23
140809_朝顔 ― 2014/08/12 01:25
140809_焼き茄子 ― 2014/08/12 01:26
昔、囲炉裏のあったころ、ナスは囲炉裏で燃える木の下の灰に埋めて焼いた気がする。
最近は、茄子の皮を厚めに剥いて、それをラップで包んでチンすると、それが焼き茄子だというのだ。
これは焼き茄子ではない、が、焼き茄子と思わないで、なんだか瓜の蒸したようなものかと思えば、それはそれで納得する。
これは焼き茄子です。
焦げ目もないのは焼き茄子ではない。と思っていたところ、あるテレビで「皮が燃えるほどまで焼く」という説明があった。
そうだ、ガスレンジで煙が出るまで焼いてみた。
皮がパリンパリンになって一部ほころびるほど放置してみた。
その後、水に入れて、皮を剥く。あっちっちです。それでも、皮は皮だけ(肉がつかない)で簡単に剥がせるのです。
旨く剥がすコツは、ヘタの下の部分に薄めに丸く切り目を入れておくのだそうです(これはTVでもそう言っていた)。
もう一つは、ヘタの上部の軸をきちんと残しておく、そこを片手でつまんで、もう片手で皮を剥けば、さほど熱くはない。
これは、実際にやってみるとわかること。
すみません、今までしたことがなかったのです(笑)。
140809_新じゃが、その後 ― 2014/08/12 23:28
俄(にわか)素材料理研究家のイガラシです!
前回掲載から、9日目。
送ってもらったじゃが芋(新じゃが)は、これで食いつくしです。
毎日同じにした訳ではないですが、皮が痛むかもと思って、畑の土の付いたままで保管(放置)しておきました。
ま、じゃが芋はイモから芽が出るような環境でなければ、ほぼ常温で一年中保存できるのですが、「新じゃが」と銘うつのはやはり、2、3日ではないかという結論に達したのです。
最初に皮を剥いたとき(8月1日)には、ほんの少し指(と爪)でこするだけで、日焼けの皮のように面白いほど剥けたのですが、なんとなく少し手ごわくなってきました。
最後に残しておいた、初日とほぼ同じ大きさのじゃが芋で再現してみました。
電子レンジのメニュー「焼きイモ」で40分ほど。やはり途中で止めた。
竹串を通すと、通るのでこのままでもよかったかも知れない。
そのあと、ガスレンジで焼いた。この有様だ。焼き茄子とちゃうで~。
調子に乗ると、こうなる例。





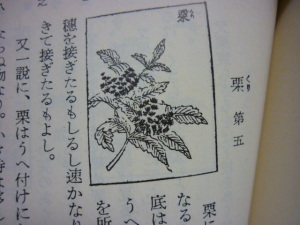








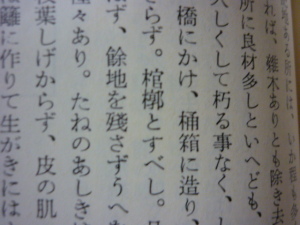

最近のコメント