130922_奥会津へ/織姫交流館 ― 2013/10/03 23:10
130922_からむし織の里からの帰り道 ― 2013/10/06 21:03
130922_奥会津/お彼岸のボタモチ ― 2013/10/06 21:09
2013年9月22日。
本日のお昼。
ジュウネンのボタモチと、
味噌付き焼き握り飯。
ボタモチは、前夜からうるかしておいた餅米を炊く。
ウルカスとは、乾燥食物を水に浸して水分を吸収させることである。
つまりは、節(せつ)の食というのは大抵は前日(またはそれ以前)から準備されるのである。
たまたま出かけて「ボタモチ喰いっちなぁ」などと言われても、被訪問者は困るのである。
「仏様に、上げもうさねとなんねから」
アゲモウスとは、お供えすること。
ナンネカラは、しなくちゃいけない、というほどの意味であるが、強制されてとかいったことではなく、日常の暮らしの節のこと。
一日の生活で言えば「顔を洗う」といったこととほとんど同じ類の当たり前のことなのです。
ところで、奥会津では、「おはぎ」も「ボタモチ」と言っていました。それが一般的だったかどうかは判りません。
が、まことしやかに「『春は牡丹(ボタン)』『秋は萩(ハギ)』なので、季節の彼岸によって使い分ける(フフン!)」という節がありますが、僕は信じない。
どっちも「ボタモチ」なのだ。
つまり餅米を使って作るのであるが「餅」にはしないところからの形状修飾としての「ボタ」が付いたのだと思う。・・・もっと見る
9月25日 22:38
(某FBより)
と、書いてみたら、ボタモチは、元々は、仏様にお供えするところから、
「仏陀餅」から遷移したのではないだろうか、と、とんでもない妄説が出てきてしまいました。
しかし、その元となった「仏陀餅」という言葉はきいたこともない。
では、大仏様ならどうだろうか、観光土産で「大仏餅」とかないだろうか。
と、考えていくと、ボタモチの形状は「ダイブツ様」の頭の形からきたとか、、、
130922_奥会津にて/からむし工芸博物館 ― 2013/10/06 21:53
「からむし工芸博物館」では、『会津野尻組の戊辰戦争』という企画展を開催している。
2013年12月1日まで、企画展開催中です。
明治元年(慶応四年)の戊辰戦争時の金沢藩の史料に、当時の大芦村の地図があったことが今年になって判明したのである。
調査したK氏は、それを金沢市立玉川図書館に赴き、戊辰戦争関係の史料を閲覧して見つけられたのです。
「からむし工芸博物館」のロビーには、7月から先行してこの地図の写真を展示していました。
勿論、撮影お断りでした。
今回、それらの写真も展示室内に、展示してある。勿論、撮影禁止です。
ロビーに飾ってあるところで、メモ帳を出して書き写すのは少し恥ずかしいてらいがある。
が、展示室内では、カメラを出すわけではない。
展示室内では、メモ帳(貰ったパンフレットチラシなどの裏紙ではない)と、ボールペンを出すのはなんら注意されることもないのである。
それに、展示室内は混雑している様子もないので、書き写してみたのがこのメモでした。
はじめに絵図を見た時には、どうも方角位置がわかりにくかった。
実際の絵図とはだいぶ違った図になってしまったが、それでも道路と川を書いていくと、大芦集落のこの図(『戦争等巨細録/大芦縮図』)は、とても正確かつ、現在もほとんどその状態であることがわかったのでした。
山崎の先(中組の手前、宮田と元の小学校のあたり)が微妙に違うが、ひょっとして、集落の家の数までがほとんど同じではないか!。と。
もしも昭和村大芦に行ったことのある(または住んでいらっしゃった)方で、この図を見て、まさかね、と思う方は、このわたしの書いた図が違っているだけなのです。
ホントです、「からむし工芸博物館」に行って、実物(拡大複写絵図)を見てください!(笑)
130922_奥会津にて/夕景散歩 ― 2013/10/12 00:16
2013年9月22日。奥会津昭和村にて。
そろそろ夕方に近かった。
が、見ておきたいところがあったので夕食前まで散歩した。
こんなになぎ倒されていても、最近の稲刈り機械は、下から櫛のような装置もあって、刈取ってしまうらしい。
ただ、このなぎ倒された稲の穂が、地面について再び水を含むと、芽を出してしまうらしい。
小さな田んぼ(とは限らないかもしれないが)では、株毎に真っ直ぐにはならずとも、倒れた稲を数株ずつまとめて、結わえて稲穂が地面にくっつかないようにしているところもあった。
どこで聞いたか(読んだか)忘れてしまったが、こうべを垂れる頃の稲は、倒れやすいのは当たり前になっている。
その時に、田んぼにヒエが混じっていると、強い茎と垂直力で、強風による稲の倒壊を防ぐ力もある、のだとか。
村の老人ホームの施設の建物。明かりの場所は、その広間だろうか。
赤い(オレンジ)色の明かりがともる。
少し行くと、赤い(オレンジ)色のデジタルが光っている白いポストのようなものがある。
老人ホームと道を隔てた「すみれ荘」という施設である。
ここには診療所と、幼稚園(保育園)の建物がある。
植栽の木には赤い木の実がたわわと生っていた。
その敷地境界の位置で、赤い(オレンジ)色にデジタルに発光しているのが、この白いポストである。
環境放射線量モニタリングポストという。
どこからか飛んできて居座っている放射線というものを調べて24時間365日どこかに告げ口する装置である。
普通のポストというのは、伝えたい人がそのポストに伝えたいことを何らかの形(ハガキだったり封筒だったり)にして、伝えたい相手に届くことを期待して投函するものである。
この白いポストは、そんな流暢なものではない。モニタリングポストというらしいのである。この白いポストは、隠密のようなものである。
宛先も決まっているのである。
勝手に撒き散らして、空気と同じ扱いの無主物として扱い、「お前のところも調べてやるからな」というお仕着せの装置である。
赤いポストのような投函口というのはない。
従って、このポストに向かって何か気持ちを伝えようと思っても、普通の手段ではその伝える術(すべ)もないのである。
既に稲刈りを済ませて、ネリ(はざ)に架けて乾燥させている田んぼがあった。
村内でも早場米になると思う。
どうも、この田んぼは田植えも「手植え」をした田んぼではなかろうか。
刈取った跡の根の配列を見て判断したのだが、こんなに曲がって植える技術を持つ田植え機はないだろう。
それとも、最近は、「手植え風田植え機」などというのもあるのか?ないない。
二階の灯りから、こちら(散歩中)を見ている人影があったので手を振ってみた。
はたして、新一郎さんでした(^^;。
二階の玄関から出ていらっしゃった。
旧中津川小学校前。
小学校があったことの面影は、少し広い空地と、校門の松の木と、今でも校門の石には陶器製の「中津川小学校」の表札が残っている。
歩いているうちにだいぶ暗くなってきた。
そろそろ、今回の折り返し場所。
山の端の陽が隠れると、まばたきする間に
だるまさんが転んだ、闇闇、だるまさんが転んだ、闇闇闇闇
だーるまさん、
まさにたそかれ(誰ぞ彼?)の時間となってしまったのでした。
下中津川の熊野神社の参道入口の社標の石。
少し見えにくいが、「熊野神社」の文字はくっきりと。
明るくして写すと、「熊野神社」の上に「村社」とある。
その文字がセメントか何かで埋められている、というのである。
この発見とそのことをK氏が、最近ブログで書いていたのです。
そして、この「村社」の文字は、第二次大戦後のGHQの指導で消されたというのです。
ますます、ほんとに真っ暗になってきた。
熊野神社。鳥居の向こうが社殿。
農道に曲がって戻り道。
デジカメの感光度を最大にしてみた。
田んぼも真っ暗で見えなくなった。
右を見ると家の明かりが見えるが、左側は山。
その山すそに、青と赤とで点滅する明かりが見える。
どうやら、野生動物避けの点滅装置らしい。
自分は明かりの装置も持参していないのである。
真っ直ぐな道なので迷うことはないが、少し寂しいし怖いぞ。
歌でも唄うか。
公民館の建物裏、フラッシュを焚いてみた。
熊が写っていた!などということはなかった。
行きにも見かけた、村の老人ホームの施設の建物。
赤い(オレンジ)色の明かりは、外から見ても、なんかほっとします。
・・・
翌朝、束原宗三郎商店に、タバコと、ついでのお使いで豆腐を買いに寄った。
「にっしゃ、あーだ時間にどこさ行って来た」
夕方の散歩を見られていたのである。
「熊野神社まで散歩に行ったら真っ暗になった」
「おっかなくねーのが、熊が出てんだぞ!」
正しく恐れる とはこういうことである。
よそ者の無謀さ。
130923_奥会津/離郷の朝 ― 2013/10/13 01:35
2013年9月23日。奥会津昭和村にて。
冬の準備、雪囲い。違います。
夏の後片付けです。
これは、畑のトマトの畝に建てたハウスのビニール。
水で洗って、乾かして、もう一回裏返して乾かして、また来年使うのです。
しかし!平成22年の時刻表でいいのか。
延べ、2日かけてヒエ抜きをした田んぼ。
とりあえず、満遍なく抜いたあとの図。
田んぼに入って歩いて見ると、ヒエ以外の雑草、ウマズラなんとかとか、小さな葉っぱだけの水草とか、場所によって植生が違うのである。
稲の生育(稲穂の熟度)は、まだ黄金色とはいえない、奥のほうはまだ青い。
水が抜けていない状態で、長靴で歩くと、泥濘(ぬかるみ)状態にはまり、歩けない。
田んぼの奥の山すその自生の栗。
元田んぼ。白い花は蕎麦の花。
最近この実の名前を知った。
「ボケ」というらしい。山ブドウではなく、「野ブドウ」ということも。
130923_奥会津/喰丸通過 ― 2013/10/13 02:40
130923_奥会津/奥奥会津 ― 2013/10/18 01:27
2013年9月23日。
奥会津昭和村からの帰り、義弟の車に同乗。
途中の気になるラーメン屋で昼飯にしようというような時間に出かけたので、寄り道時間もそこそこにあった。
もっとディープな奥会津をドライブした。
行き先の交通標識が、「只見、魚沼」と出てくる。
むかし、森に在った時には、奇形ゆえに伐採されず、そして大きく生き延び、そして神木として祀られたであろう木々。
これは、室内に展示してある。
どれくらいの大きさかを比べるために、義弟に並んでもらって写した。
遠近法によるトリックではない。人物はこの木の真横に寄りかかっているのです。
この工房の通りを面した反対側は、定尺となるような木材と(材木板)と木材チップの工場。
おそらく地元では有名な林業会社かもしれません。
130923_奥会津から南会津/前沢集落へ ― 2013/10/18 01:45
昔は、蔦で編んだ吊り橋ひとつあったかなかったかというほどの峡谷の橋。
そこに、堅牢な新しい橋も作られようとしている。
トンネルも出来ている、どっちが先かはわからないが、大型車両がバンバン通れる設備。
観光県なので、大型バスなどがバンバン走らないと困るのか?
人がそんなに行き来するとは思えないのである。
つまり、人以外のモノを移動させるため?
「道の駅」が各地にある。
国道をドライブすると、売らんかなの沿道沿いの個人商店とはちがうことと、
「道の駅」という統一ブランドとなって、サービス(トイレ、食事など)がほぼ均質化(安心感ですね)している。
その上、その敷地に出店している商品も地産品が多い。
売子も、近所の個人農家の副業商売感(安全感ですね)で、話しかけやすいとか。
勿論、他の広域知名度の高い業者のいわゆるみやげ物などもある。
地域活性化、関連雇用促進などにも一役買っているらしい。
それはそれで、いわゆる三方よしの構図とはなっているようでもある。
のであるが、イベントパンフや幟(のぼり)を見ると、どこもかしこもスタンプラリーかい!
といった、色々な補助金交付金取りを本業として仕掛けをしている他所のイベント業者の影もちらりと見え隠れする。
第三者の業者がいなければ、こんな施設自体も地元の人だけで実現できないことも重々承知はしている。
ま、どこまでが絆とつながりと、利権となのかは、わからない。
勿論全部がそうだとは言うわけではない、応援したいインディーズも、あ・り・ま・す・よ。
(少し睨まれそうだが、書いてしまった(笑))
130923_奥会津から南会津/前沢集落にて ― 2013/10/18 02:13
2013年9月23日。前沢集落にて
2013年9月23日。前沢集落にて
受付にて、
「この集落は住民が住んでいますので、指定された場所以外の庭や家の中には入らないで下さい」「はい」
「畑にも入らないで下さい、作物もなっていますが、採らないで下さい」「はい」
「中をご覧になれる家があります。その場所はここ(地図の場所をしめす)です」「はい」
「ただ、今は屋根葺き工事でブルーシートが掛かっています。立入り禁止の看板もあります」「はい?」
「それでも大丈夫ですから、入ってかまいません。その家には入ってご覧下さい」「はぃ」
「集落の一番奥に××神社があります、そこまでも行けます。」「はっ」
「そこは、近づくとスズメバチがいますので注意して下さい。騒がなければ大丈夫です」「はち・・・」
「入場料はお一人300円です。ではごゆっくりどうぞ」
この場所は、完全に居住地区で、住人が観光客相手に積極的な生活はしていない場所らしい。
つまり、対比しては失礼ではあるが、大内宿のようにそこの各家の住人が客商売で生計を営んではいないらしいのです。
中に入ると、集落の道沿いに、商店などは1軒もない。ところどころに野菜、山菜などの無人販売所はある。
それも、ひょっとすると観光客向けではなく住民同士の互助設備かもしれない。
ホントかどうか、詳しい「前沢集落」については、興味のある人はとりあえずWebででも検索してください(^^;
この橋だけが、集落への通路となる。
正面の3本の木、大木といってもよい木であるが、葉っぱを見ると「桑の木」なのである。
後で、説明の方に義弟が尋ねていた。やはり桑の木でした。
昔昔見た、桑の木は低木用に剪定してあったはずという。
御蚕様(養蚕)に桑の葉を採取するために、剪定した(手間をかけた)のであの高さ(せいぜい樹高2m)なのだというのです。
でも、桑の葉自体も大きいような気がした。
昔昔採って喰った、桑の実もなるはずだというのです。
その実は見つけられなかったが、この木の大きさだぞ。
「桑の実もブドウの巨峰ぐらいに大きくなるのか?」と訪ねたあたりから、すこしハナで笑われてしまった。
この家だけは、内部に入れる家。移築してきたらしい。
説明の係員(女性)がいらっしゃった。
奥会津弁なまり(実は奥会津なまりは会津弁ではくくりきれないほどに多様なのです)ながらも、標準語で丁寧に説明してくださる。
土間から板場と、部屋の作りと、大黒柱の話と、農具の話と。
感心して話を聞きながら、「実は、隣村の昭和村に住んでいたんだけど」と言ったら、「なーんだ、昭和村にはまけっぺ(かなわない)!」ときた。
南会津町は、元々南会津郡「田島町」が、平成時代になって近隣の村をひっくるめて合併してだだっ広い「南会津町」となった。
おそらく、地域文化歴史的には、昭和村と同じような村も「南会津町」になってしまった。
隣の南会津郡「只見町」も同じような経緯でだだっ広い「只見町」である。
その「境界」地域といってもよいような、大沼郡「昭和村」と南会津郡「檜枝岐村」は、南会津町にも只見町にも組しない(出来なかった)で、今でも「村」として残っている。
最近のブームも手伝ってかも知れないが、
南会津町は、町内施設名や地域名の一部は、南会津といわないでわざと「奥会津」と自称しているところがある。
こういうのは、すこしずるいぞと村出身者は思ってしまうのである。
もっとある。大内宿を擁する南会津郡「下郷町」、ここでは地元企画の「観光土産」の生産者ラベルに「下郷ムラおこし」などと使っている。
マチになったんだから、潔(いさぎよ)く「マチおこし」といいなさい!と思ってしまう。
ついでに書いておくと、奥会津地域の隣町の大沼郡「三島町」。
この町は、「日本一きれいな村」という全国組織の広域団体に「日本一きれいな村」の一つとして認定されている。
なんでこんなときだけ、「村」というのだね!と思ってしまうのである。
ま、昭和村は「日本一きれいな村」という名の三島町の隣の『本当の村』である。
あ、こんな話を書こうとしていて、ブログ掲載がどんどんと遅れたわけではないのだが。
さっと流して、一旦アップして9月の奥会津探訪ブログはこれでおしまい。
いつか又、再訪時にもう一度、一枚一枚の写真に能書きを垂れたいものだ(^^:。
御仏壇、ここの仏様(ご位牌)はどこかに移られたらしいので何もない。
神棚、ここには、おそらく神様が今でも住んでいらっしゃるのだと思う。
昭和村小中津川の束原一族と同じ家紋を見つけた。
「なんだ」昭和村大芦の赤田(あかだ)と同じだ。と思った。
どうもこのあたりの表記は、絶対にウケを狙っていると思いました(笑)
公園入口の無人販売、「廿いスエカ」「一玉 500円~300円」と書いてある。
集落内をただ散歩するだけなら、おそらく2、30分も掛からない。
屋内開放展示の場所には、説明員の方がいらっしゃる。
交代で複数の方がいらっしゃるのかもしれない。
たまたまいらっしゃった方が、アタリだったかどうかは分かりませんが、とても説明好きなのと、マニュアル通りの説明ではなく、当意即妙の受け答えも楽しかった。
時間があれば、半日いても飽きないかも知れないが、そんなに居座られたら迷惑かもしれませんネ。
















































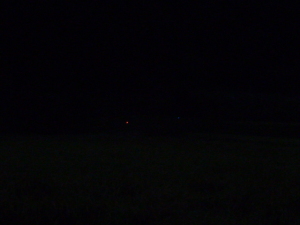





































































最近のコメント